STEP 4. 工事監理
内容:工事の指導監督、工事変更の処理、施工図の検査、完了検査申請
期間:4〜6ヶ月
■ 工事監理の進め方 ■

設計監理にかかる業務はどれもが大切ですが、中でも工事監理は重要です。
せっかく作成した綿密な図面があってもその通りに工事が行われるかは別問題だからです。
実際に住宅を建てる上で、設計図面通りの適切な材料が使われているか、欠陥住宅の要因でもある基礎・床下・柱梁など壁内部に隠蔽されてしまう箇所が問題なく施工されるか、工程通りに工事が進行しているか、などを建主さんに代って頻繁に現場に出向き、現場写真を撮影し、必要に応じて検査を行い、施工者と打合せをし、工事の指導監督を行います。
その記録は「工事監理記録」としてまとめ、竣工後、建主さんに納品しています。
一般的には建物が完成するまで現場には関心のない方が多いようですが、家づくりでは人と人との信頼関係がとても大切なのです。
そこで当事務所では、建主さんにもなるべく現場に足を運んでもらい、色決めや変更の承認などをいただいたり、現場の職人さん達ともコミュニケーションをとっていただくようにしております。
実際に我が家が形になっていく経過を見れることはとても楽しく、ワクワクするものです。
木造住宅の場合、工事着工と同時に地鎮祭を行い、それから約1ヶ月で上棟式となります。通常、梅雨時・厳冬期を避ければ約4ヶ月半くらいで完成します。
床のオイル塗りや壁塗りなど、我が家のため、また予算節約のために自分たちでも何かやってみたいという建主さんのご要望に対しても、施工者と工程を調整し、柔軟に対応しております。
竣工直前には行政機関に完了検査申請を代行して行い、係官によって完了検査が行われます。(完了検査申請手数料<平均的な木造住宅で¥19,000>は建主さんの実費となります)
完了検査に滞りなく合格し、施工者の自社検査、設計事務所の監理検査、不備事項の手直しを経て建主さんに引渡しとなります。
関連リンク:for Clients./ 09〜13
ここまで読み進めていただいた皆さん、いかがでしたか?
「はじめに」や「基本設計」の項でも少し触れましたが、設計料が無駄だと感じますか?
理解ある方には納得してもらえたかもしれませんし、そんな手間がかかって面倒臭いこと必要ないと思われた方もいるかもしれませんね。

建主さんと設計者の住まいに対しての情熱や費やした時間が最終的な「住まい」の出来を左右することは多分にある、と私は信じて止みません。
住まいづくりはほとんどの方が初めての経験で、わからないことばかりで当たり前なのです。
だからこそ、安直に住まいを建てようなどと考えずに、ぜひ当事務所を頼ってみてください。
疑心暗鬼にならず、雑談も交えながらリラックスして話し合い、信頼関係を築いていくことができるのであれば、必ずやご期待にお応えすることができるでしょう。
![]()
建主さんのご感想は こちら
前者を「さらかん」後者を「たけかん」ともいい、工事監理は設計事務所が、工事管理は施工者が担う業務。
「工事監理」の内容は上記の通り。「工事管理」では請負金額に基づき、施工者が「材料や職人の手配」「工事工期のスケジュール調整」「現場の安全対策」などをすること。
工事管理のみでは施工者が利益を優先するあまり、良い建物を誠実につくろうという意識よりも、安価な材料を使ったり、手間を極力省いたり、工事を早く終わらせようとする傾向が強くなる。
なお「工事監理」は施工者とは営利関係をもたない建築設計事務所でなければ行うことが認められていない。
 無料相談
無料相談 LINK
LINK 設計理念
設計理念 料金表
料金表 住宅作品フォト
住宅作品フォト お問い合わせ
お問い合わせ オープンハウス
オープンハウス ブログ
ブログ TOP
TOP About...
About... for Clients.
for Clients. Process
Process CG
CG WORKs
WORKs VOICE
VOICE Q&A
Q&A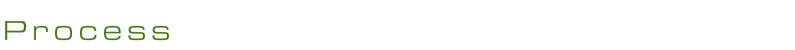
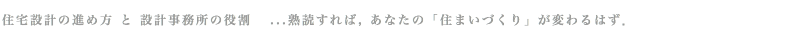
 Process TOP
Process TOP




 サイトTOP
サイトTOP